
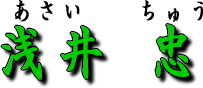
安政3年(1856)~明治40年(1907)52歳

佐倉商工会議所
佐倉NAVIで読む
忠は、日本の洋画を代表する画家であり、日本を代表する洋画家の一人として日本だけでなく世界中から高い評価を受けている人物なのです。
忠は、江戸時代末期、日本国中が開国、攘夷と大騒ぎをしていたころ佐倉藩の江戸屋敷で生まれました。佐倉藩においても藩主堀田正睦が老中として日本の将来のために必死に働いていました。そんな中で忠は少年時代を佐倉で過ごし明治維新を迎えました。
明治9年(1876)、上京し工部美術学校に入学した忠は、ここで外国人教師から本格的な西洋画の手ほどきを受け、めきめきと才能を開花させていきました。明治27年(1894)に始まった日清戦争では、新聞社から画家として中国に派遣され、戦場の様子を絵画に表しました。「花園口上陸図」などは、忠の代表的な作品の一つとして有名です。そして、明治33年(1900)、忠はついに念願のフランス留学を果たしました。この2年半にわたるフランス留学が忠の絵を完成させたのです。それは、明治34年(1901)に描き上げた「グレーの秋」という作品に表れています。明治35年(1902)に帰国した忠は、京都に住まいを移し京都高等工芸学校(今の京都工芸繊維大学)の教授として生徒に西洋画を教えるかたわら、自らも聖護院洋画研究所(後の関西美術院)を開き、梅原龍三郎や安井曾太郎といった次の時代の洋画家たちを育てるとともに日本洋画界の基礎を築き、明治40年(1907)、その生涯を閉じました。